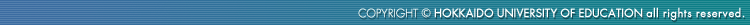|
1. |
2026/01~2026/01 |
「2025年度核融合科学研究所スクーリング・ネットワーキング事業」における講演「STEM教育で核融合リテラシーを高めよう」 |
|
2. |
2025/11 |
釧路・根室管内高等学校長研究協議会における講演「教職の魅力、再発見!~中・高・大・地域での探究がつなぐ育成のカギ~」 |
|
3. |
2025/11~2025/11 |
教員研修会における講演「STEAM教育実践論」 |
|
4. |
2025/07~2025/08 |
教員研修会における講演「STEM教育実践論」 |
|
5. |
2025/07 |
北海道釧路湖陵高等学校アカデミックインターンシップでの講演「探究とは」 |
|
6. |
2025/02 |
SSTA(ソニー科学教育研究会)研修会での講演「STEAM 教育の視点で『科学好きな子ども』を育成するための授業デザイン」 |
|
7. |
2025/01 |
第13回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 実行委員会委員 |
|
8. |
2024/12 |
島根大学教育学部附属学校園での研修会講師「教育現場で活用するテキストマイニング:児童・生徒の声を効果的に分析する手法」 |
|
9. |
2024/10 |
釧路少年少女発明クラブでの講師 |
|
10. |
2024/10 |
北海道大学エネルギー教育研究会10月例会における講演「エネルギー教育に関するカリキュラム構成について~STEAM教育と新学習指導要領との関連から~」 |
|
11. |
2024/09 |
石垣市立明石小学校(沖縄県)におけるSTEAM教育に係る出前授業と職員研修 |
|
12. |
2024/09 |
竹富町立小浜小中学校(沖縄県)におけるSTEAM教育に係る出前授業と職員研修 |
|
13. |
2024/09 |
ワークショップ講師:北海道新聞・北海道教育大学「子ども未来キャンパス」in 旭川 なるほど?!音楽教室Ⅱ~木琴工作でSTEAM教育を体験しよう~ |
|
14. |
2024/09~2024/09 |
道北おとぼけキャラバン[STEAM]in中頓別「リバーシブル木琴チャイムをつくる」 |
|
15. |
2024/08~2024/09 |
道北おとぼけキャラバン[STEAM]in留萌「リバーシブル木琴チャイムをつくる」 |
|
16. |
2024/08~2024/08 |
道北おとぼけキャラバン[STEAM]in深川「リバーシブル木琴チャイムをつくる」 |
|
17. |
2024/07 |
第3期ソニー科学教育研究会(SSTA)エリア別テーマ研修会 講師 |
|
18. |
2024/07 |
北海道釧路湖陵高等学校「Koryo Quest」での講演「探究学習とは」 |
|
19. |
2024/05 |
釧路市少年少女発明クラブでの講演 |
|
20. |
2024/04 |
釧路青年会議所 2024年度 4月第一例会における講演「探究学習について、研究者の立場から」 |
|
21. |
2024/02 |
第3期ソニー科学教育研究会(SSTA)エリア別テーマ研修会 講師 |
|
22. |
2024/02 |
北海道興部高等学校への出前授業「生活設計・進路講話」 |
|
23. |
2024/01 |
第12回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 実行委員会委員 |
|
24. |
2023/11~2023/11 |
教育学博士が監修した新しい教育体験観光ミニ体験会(木琴ドアチャイム作製) |
|
25. |
2023/11~2023/11 |
第3期ソニー科学教育研究会(SSTA)エリア別テーマ研修会での講演「中学校理科で育むべき資質・能力と、中学校理科の現場から見た小中連携の課題」 |
|
26. |
2023/02~2023/02 |
道北おとぼけキャラバン[STEAM教育]木琴&音楽づくり in 富良野市立山部小学校 |
|
27. |
2023/01 |
第11回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 実行委員会委員 |
|
28. |
2022/08~2022/08 |
道北おとぼけキャラバンSTEAM「リバーシブル木琴チャイムづくり」 in 留萌市立緑丘小学校 |
|
29. |
2022/02~2022/03 |
道北おとぼけキャラバン[STEAM教育]木琴&音楽づくり in 留萌市立緑丘小学校 |
|
30. |
2021/01 |
第10回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 実行委員会委員 |
|
31. |
2020/10 |
釧路市立清明小学校校内研修会 講師「理科の授業づくりのヒント」 |
|
32. |
2020/01 |
第9回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 研究発表「地震波と音の共通点を見つけよう」 |
|
33. |
2019/12 |
標茶町立虹別小学校校内研修会 講師「プログラミング教育の考え方」 |
|
34. |
2019/12 |
令和元年度地域連携研修「プログラミング教育」の授業づくり研修会での出前授業 |
|
35. |
2019/08 |
幕別町立札内北小学校への出前授業「プログラミング学習」 |
|
36. |
2019/07 |
釧路市立清明小学校校内研修会 講師「小学校におけるプログラミング教育の考え方」 |
|
37. |
2019/01 |
釧路町教師力向上研修会 講師「小・中学校におけるプログラミング教育について」 |
|
38. |
2019/01 |
第8回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 実験屋台「孔雀石(くじゃくいし)って知ってる?」 |
|
39. |
2018/12 |
音更町立下士幌小学校 校内研修会講師「プログラミング教育の考え方」 |
|
40. |
2018/12 |
音更町立下士幌小学校への出前授業「プログラミング学習」 |
|
41. |
2018/12 |
厚岸町教員授業力向上研修会(冬)講師「プログラミング学習とは」 |
|
42. |
2018/12 |
第122回 たんちょう先生の実験教室 「新指導要領先取り講座 見えない放射線を確かめよう」 |
|
43. |
2018/11 |
厚岸町立教育研究所 道徳部会講師「道徳の評価」 |
|
44. |
2018/11 |
十勝へき地・複式教育研究連盟事業「複式教員研修」兼「教師力向上ワークショップ」講師(道徳) |
|
45. |
2018/10 |
標茶町立虹別小学校 校内研修会講師「プログラミング教育の考え方」 |
|
46. |
2018/10 |
標茶町立虹別小学校への出前授業「プログラミング学習」 |
|
47. |
2018/09 |
道北おとぼけキャラバン「ヴァイオリンものしり音楽鑑賞教室」 in 和寒町立和寒小学校 |
|
48. |
2018/09 |
和寒町立和寒小学校への出前授業「昆虫の動きを学んで表現しよう」 |
|
49. |
2018/08 |
厚岸町立太田中学校 校内研修会講師「道徳の評価」 |
|
50. |
2018/08 |
鶴居村立幌呂小学校 校内研修会講師「ゼロからはじめる 出前授業を通して学ぶプログラミング教育」 |
|
51. |
2018/08 |
鶴居村立幌呂小学校への出前授業「プログラミング学習」 |
|
52. |
2018/08 |
北海道教育委員会 授業改善テクニカルサポート講師(道徳) |
|
53. |
2018/06 |
浜中町立散布小中学校 校内研修会講師「小中連携によるカリキュラム作成」 |
|
54. |
2018/05 |
道北おとぼけキャラバン in 屈斜路和琴「楽器について楽しく学ぶ」音楽教育コンサート |
|
55. |
2018/01 |
第7回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 研究発表「地震予知の是非を検討してみよう」 |
|
56. |
2017/10 |
釧路市立城山小学校への出前授業「総合的な学習の時間」 |
|
57. |
2017/09 |
鶴居村立幌呂中学校 校内研修会講師「特別の教科 道徳」に向けた評価と授業づくり |
|
58. |
2017/08 |
北海道教育委員会 中堅教諭等資質向上研修(10年経験者研修)講師「ミドルリーダーの役割」 |
|
59. |
2017/07 |
北海道教育委員会 授業改善テクニカルサポート講師(道徳) |
|
60. |
2017/06~ |
青少年のための科学の祭典釧路大会「サイエンス屋台村」実行委員会 |
|
61. |
2017/01 |
第6回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 研究発表「お菓子と地形の秘密」 |
|
62. |
2016/09 |
釧路工業高等専門学校FD研修会講師 |
|
63. |
2016/01~ |
ジオ・フェスティバル in Kushiro 実行委員会委員 |
|
64. |
2016/01 |
第5回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 研究発表「雲と山から天気を考えよう」 |
|
65. |
2015/08~ |
釧路市立高等看護学院講師(生化学) |
|
66. |
2015/07 |
釧路町立教育研究所理科部会 講師 |
|
67. |
2015/01 |
第4回 ジオ・フェスティバル in KUSHIRO 研究発表「雲を上から見てみると」 |
|
10件表示
|
|
全件表示(67件)
|